Entries
(1/26) 紙芝居
(1/26) 紙芝居
私は小学校に入ったあとも近所の子どもたちとまったく縁がなく
なった訳ではなかった。前に述べたように孤立児で人付き合いが下
手だから誰とでもという訳にはいかないが、隣近所の子どもたちと
はその後もいささかのつきあいがあった。
将棋を指したりプラモを組み立てたりゴロベースをしたり町内会
の子供祭にだって参加していた。そんな近所の子供たちが、毎日の
ようにたむろしている場所、それは駄菓屋か公園。だから学校は違
っても放課後そこで落ち合えば彼らの次の遊びから帯同できたので
ある。
母はその現実をよく承知していたから公園が見渡せるタバコ屋の
おばさんに私のスパイを依頼していたのだった。
あえて説明は無用かもしれないが、駄菓子屋というのはその名の
通り子供のささやかな小遣いでも買える安いお菓子を専門に売って
いるお店のことで、我が家に一番近い駄菓子屋は児童公園そばにあ
った。
そこは小学一年の頃わざわざ新築してまでお店を開いたくらいだ
から当時はそれだけ子供が多かったのだろう。
私も近所の子供たち同様五円十円握りしめてその社交場へ通った
一人だが、おやつは家で別に用意されていたから駄菓子屋でお腹一
杯にになってはいけなかった。
それだけではない。私の場合、試験管に入ったゼリーは体にあわ
なくて、食べれば必ず蕁麻疹だったから母親からは絶対に手をつけ
てはいけないと言われていたのだが、友だちに「勇気がない」と言
われると手を出さないわけにはいかず、よく母を徹夜させてしまっ
たのを覚えている。
一方、公園には紙芝居がやってきた。拍子木につられて集まった
子ども達に水飴や薄いせんべいなんかを売ってから絵物語りが始ま
る。当時は個別にビニール掛けがしてあるなんてことはないから、
水飴にはハエがたかるし、せんべいもおじさんの薄汚れた手で手渡
しされるからかなり不衛生だ。
おじさんは「買わない子は見ちゃいけないよ」なんて因業なこと
を言っていたが、それはかぶりつきの場所が確保できるかどうかの
差でしかなかった。
お菓子を買わない子は離れてみていればよかったのである。
そんな可哀想な子(?)に水飴をやると私は少し離れた処を散歩
して時間をつぶす。おじさんの紙芝居は他の子にとっては面白いも
のだったかもしれないが、私はごく幼い頃をディズニーの絵本で育
っているせいか、あの毒々しいイラストが好きになれなかった。
ならば水飴も買う必要もないわけだが、これまた、不思議と義理
だけは欠かさなぬ子だったのである。
私は小学校に入ったあとも近所の子どもたちとまったく縁がなく
なった訳ではなかった。前に述べたように孤立児で人付き合いが下
手だから誰とでもという訳にはいかないが、隣近所の子どもたちと
はその後もいささかのつきあいがあった。
将棋を指したりプラモを組み立てたりゴロベースをしたり町内会
の子供祭にだって参加していた。そんな近所の子供たちが、毎日の
ようにたむろしている場所、それは駄菓屋か公園。だから学校は違
っても放課後そこで落ち合えば彼らの次の遊びから帯同できたので
ある。
母はその現実をよく承知していたから公園が見渡せるタバコ屋の
おばさんに私のスパイを依頼していたのだった。
あえて説明は無用かもしれないが、駄菓子屋というのはその名の
通り子供のささやかな小遣いでも買える安いお菓子を専門に売って
いるお店のことで、我が家に一番近い駄菓子屋は児童公園そばにあ
った。
そこは小学一年の頃わざわざ新築してまでお店を開いたくらいだ
から当時はそれだけ子供が多かったのだろう。
私も近所の子供たち同様五円十円握りしめてその社交場へ通った
一人だが、おやつは家で別に用意されていたから駄菓子屋でお腹一
杯にになってはいけなかった。
それだけではない。私の場合、試験管に入ったゼリーは体にあわ
なくて、食べれば必ず蕁麻疹だったから母親からは絶対に手をつけ
てはいけないと言われていたのだが、友だちに「勇気がない」と言
われると手を出さないわけにはいかず、よく母を徹夜させてしまっ
たのを覚えている。
一方、公園には紙芝居がやってきた。拍子木につられて集まった
子ども達に水飴や薄いせんべいなんかを売ってから絵物語りが始ま
る。当時は個別にビニール掛けがしてあるなんてことはないから、
水飴にはハエがたかるし、せんべいもおじさんの薄汚れた手で手渡
しされるからかなり不衛生だ。
おじさんは「買わない子は見ちゃいけないよ」なんて因業なこと
を言っていたが、それはかぶりつきの場所が確保できるかどうかの
差でしかなかった。
お菓子を買わない子は離れてみていればよかったのである。
そんな可哀想な子(?)に水飴をやると私は少し離れた処を散歩
して時間をつぶす。おじさんの紙芝居は他の子にとっては面白いも
のだったかもしれないが、私はごく幼い頃をディズニーの絵本で育
っているせいか、あの毒々しいイラストが好きになれなかった。
ならば水飴も買う必要もないわけだが、これまた、不思議と義理
だけは欠かさなぬ子だったのである。
(1/27) おやつ
(1/27) おやつ
私の家ではおやつが出た。
今の人に言わせると「それがどうした?当たり前じゃないか」と
思うかもしれない。しかし、昭和の30年代というのは、まだまだ
貧しい時代で、多くの家庭では子供に小遣いを与え駄菓子屋で何か
買っておやつにするというのが一般的なスタイルだったのだ。
ただ我が家に限って言えば、絶対的な権力者である母親がこれを
快く思っていないこともあって、おやつは家の中で母親の膝の上で
食べるものだったのである。
そこに出てくるものとしては、水菓子か虎屋の羊羹、風月堂のゴ
ーフル、モロゾフのチョコレートあたりが多かったように記憶して
いる。いずれにしても大人のお茶会で子供の口にはあわないものが
多かった。
いえ美味しくないというのではない。ただ、コビトチョコレート
の銀紙の裏に当たりの字を見つける喜びや細いタコ糸を引寄せた瞬
間大きな三角飴が動いた感動に比べればそれはつまらない行事だっ
たのだ。
おやつの時間というのは、母が近所のお母さんたちを招いて井戸
端会議を主催する時間でもあったから母にとってはそこに私が座っ
ている方が何かと都合が良かったのである。
母にとっての井戸端会議は、
「昨日P社のデザイナーさんに頼んでおいたこの子の服が届いた
の」と言ってはその服を私に着せてファッションショーを始めたり、
「今度この子が学級委員に選ばれたの」と言ってはその証のバッチ
をわざわざ制服から外させて閲覧させたりとやりたい放題。
黙っていても何ら差し支えないことを次から次に披瀝するご自慢
大会なのだ。正直、聞いてるこっちが赤面する話も多くて、そう言
う意味でもここで出されるお菓子は美味しくなかったのである。
母のお道楽はこれだけではない。先ほど述べたが……自ら描いた
デザイン画を子供服メーカーに送って完全オーダーメードの子供服
作らせたり、外国雑誌に載ったオモチャが今はまだ東京のデパート
にしか卸されていないと聞くと、地元デパートの外商部を呼びつけ
て取り寄せさせたり。はては本屋が仕入れた全集物をそっくり買い
あさり天井まで届くような立派なガラス書棚に並べては私の部屋を
飾りたてたりもした。
いずれも大変な労力と出費だろうが、生まれながらにして母の赤
ちゃんだった私にすれば、それがごく普通の日常だったのである。
息子をダシに平気で自慢話を続ける母に嫌気が差し膝の上でその
まま寝てしまった事もたびたびだったが、今となってはむしろこん
な母の道楽につき合ってくれた近所のお母さんたちにただただ頭が
下がる思いがするのである。
私の家ではおやつが出た。
今の人に言わせると「それがどうした?当たり前じゃないか」と
思うかもしれない。しかし、昭和の30年代というのは、まだまだ
貧しい時代で、多くの家庭では子供に小遣いを与え駄菓子屋で何か
買っておやつにするというのが一般的なスタイルだったのだ。
ただ我が家に限って言えば、絶対的な権力者である母親がこれを
快く思っていないこともあって、おやつは家の中で母親の膝の上で
食べるものだったのである。
そこに出てくるものとしては、水菓子か虎屋の羊羹、風月堂のゴ
ーフル、モロゾフのチョコレートあたりが多かったように記憶して
いる。いずれにしても大人のお茶会で子供の口にはあわないものが
多かった。
いえ美味しくないというのではない。ただ、コビトチョコレート
の銀紙の裏に当たりの字を見つける喜びや細いタコ糸を引寄せた瞬
間大きな三角飴が動いた感動に比べればそれはつまらない行事だっ
たのだ。
おやつの時間というのは、母が近所のお母さんたちを招いて井戸
端会議を主催する時間でもあったから母にとってはそこに私が座っ
ている方が何かと都合が良かったのである。
母にとっての井戸端会議は、
「昨日P社のデザイナーさんに頼んでおいたこの子の服が届いた
の」と言ってはその服を私に着せてファッションショーを始めたり、
「今度この子が学級委員に選ばれたの」と言ってはその証のバッチ
をわざわざ制服から外させて閲覧させたりとやりたい放題。
黙っていても何ら差し支えないことを次から次に披瀝するご自慢
大会なのだ。正直、聞いてるこっちが赤面する話も多くて、そう言
う意味でもここで出されるお菓子は美味しくなかったのである。
母のお道楽はこれだけではない。先ほど述べたが……自ら描いた
デザイン画を子供服メーカーに送って完全オーダーメードの子供服
作らせたり、外国雑誌に載ったオモチャが今はまだ東京のデパート
にしか卸されていないと聞くと、地元デパートの外商部を呼びつけ
て取り寄せさせたり。はては本屋が仕入れた全集物をそっくり買い
あさり天井まで届くような立派なガラス書棚に並べては私の部屋を
飾りたてたりもした。
いずれも大変な労力と出費だろうが、生まれながらにして母の赤
ちゃんだった私にすれば、それがごく普通の日常だったのである。
息子をダシに平気で自慢話を続ける母に嫌気が差し膝の上でその
まま寝てしまった事もたびたびだったが、今となってはむしろこん
な母の道楽につき合ってくれた近所のお母さんたちにただただ頭が
下がる思いがするのである。
(1/28) 先頭シートの特等席
(1/28) 先頭シートの特等席
私がお世話になったバスの営業所からは五系統ほどの路線が出て
いたが、そのうち四路線は田舎の中では比較的人口の密集した場所
つまり田舎の中の都会へ行くバス。都会へ出ていくのにポンコツじ
ゃ恥ずかしいということだろうか、この四路線には親会社から比較
的新しい機種が常に導入されていて互いの性能を競うようかのよう
に走っていた。
とりわけ私が通学に利用していた路線は一年と言わず半年に一台
くらいもすると新車がおりてくるから田舎の中では花形路線だった
のだろう。営業所住まい(?)の私はその役得として、一般乗客に
先駆けてぴかぴかの車内に一番乗りすることが許されていた。特に
一番前にある二人がけクロスシートは私の寝室にもなるシートで、
私は普段からその座り心地や寝心地をつねにチェックしていたので
ある。私が電車よりバスを好んだのはこのためだった。
この先頭部分、今のバスでは前ドアの部分にあたるため存在しな
くなったが、当時は車掌さんが乗りこんでいたせいで出入り口は真
ん中に一つあればよく、運転席と同じ並びの先頭部分は乗客用の座
席になっていたのである。
ここに本来なら大人二人が座れるはずだが、私の乗るバスだけは
仕付けのなっていない不届きな幼児が一人で占拠していたため席が
一つ少なくなっていた。(^^ゞ
私はそのクッションのきいたシートをトランポリン代わりにして
遊んだり甲高い声を張り上げて運転手さんと雑談したり、ベッドと
しても使っていたがそんな不作法を一般のお客さんが注意したこと
は一度もなかった。今なら苦情が会社に来てその運転手さんは怒ら
れていたかもしれない。
私のこうした交友を今の人たちは作り話だと思っているかもしれ
ないが、昭和の30年代の頃というのは、たとえ規則は今と同じで
もその運用は大変おおらかで、今のように乗客の苦情一つで即クビ
なんて事にはならなかった。
ま、始末書ぐらいですんだはずである。
ところがそんなある日のこと、たった一度だけだが、詰め所の中
に私が入れないことがあった。小雨の降る冷たい朝で、私はその日
も当然のごとくストーブの明かりが見える小窓を叩いたが、中から
の反応は意外にも冷たいものだった。一人の運転手さんがしーしー
っと私を追い払おうとするのだ。
理由が分らぬまま部屋の奥を覗き込むと、何やら偉そうな人が仁
王立ちになって声を荒げている。よく分からないが今は駄目という
ことはわかった。
しばらく待って、それでも訓辞が終わらないから始発の停留所へ
向かってとぼとぼ歩き出すと、いつものバスがさっと私の足下に横
付けて……
「乗れ、坊主!」

注)写真は記事とは無関係です。
私がお世話になったバスの営業所からは五系統ほどの路線が出て
いたが、そのうち四路線は田舎の中では比較的人口の密集した場所
つまり田舎の中の都会へ行くバス。都会へ出ていくのにポンコツじ
ゃ恥ずかしいということだろうか、この四路線には親会社から比較
的新しい機種が常に導入されていて互いの性能を競うようかのよう
に走っていた。
とりわけ私が通学に利用していた路線は一年と言わず半年に一台
くらいもすると新車がおりてくるから田舎の中では花形路線だった
のだろう。営業所住まい(?)の私はその役得として、一般乗客に
先駆けてぴかぴかの車内に一番乗りすることが許されていた。特に
一番前にある二人がけクロスシートは私の寝室にもなるシートで、
私は普段からその座り心地や寝心地をつねにチェックしていたので
ある。私が電車よりバスを好んだのはこのためだった。
この先頭部分、今のバスでは前ドアの部分にあたるため存在しな
くなったが、当時は車掌さんが乗りこんでいたせいで出入り口は真
ん中に一つあればよく、運転席と同じ並びの先頭部分は乗客用の座
席になっていたのである。
ここに本来なら大人二人が座れるはずだが、私の乗るバスだけは
仕付けのなっていない不届きな幼児が一人で占拠していたため席が
一つ少なくなっていた。(^^ゞ
私はそのクッションのきいたシートをトランポリン代わりにして
遊んだり甲高い声を張り上げて運転手さんと雑談したり、ベッドと
しても使っていたがそんな不作法を一般のお客さんが注意したこと
は一度もなかった。今なら苦情が会社に来てその運転手さんは怒ら
れていたかもしれない。
私のこうした交友を今の人たちは作り話だと思っているかもしれ
ないが、昭和の30年代の頃というのは、たとえ規則は今と同じで
もその運用は大変おおらかで、今のように乗客の苦情一つで即クビ
なんて事にはならなかった。
ま、始末書ぐらいですんだはずである。
ところがそんなある日のこと、たった一度だけだが、詰め所の中
に私が入れないことがあった。小雨の降る冷たい朝で、私はその日
も当然のごとくストーブの明かりが見える小窓を叩いたが、中から
の反応は意外にも冷たいものだった。一人の運転手さんがしーしー
っと私を追い払おうとするのだ。
理由が分らぬまま部屋の奥を覗き込むと、何やら偉そうな人が仁
王立ちになって声を荒げている。よく分からないが今は駄目という
ことはわかった。
しばらく待って、それでも訓辞が終わらないから始発の停留所へ
向かってとぼとぼ歩き出すと、いつものバスがさっと私の足下に横
付けて……
「乗れ、坊主!」

注)写真は記事とは無関係です。
(1/29) ボンネットバス
(1/29) ボンネットバス
その日私は駐車場の隅にぽつんと置かれたボンネットに目を留め
る。普段なら「なんだボロバスかあ」で終わりだが、その日に限っ
ては、まるでそのオンボロバスが私を呼んでるような気がした。
今でこそどこにもいなくなってしまったからみんなで「懐かしい」
なんて言って乗りに行くけど、当時の常識ではボンネットの走る処
はど田舎。
「お前んとこまだボンネットかよ」なんてバカにされたもんだっ
た。
営業所で見かけたこのバス、型式も古そうだし、いつ見てもタイ
ヤやボディーが泥だらけ。エンジンを掛けると人一倍黒い煙を出す
し、走り出す瞬間も、「おや壊れたんじゃないか」って心配するほ
どもの破裂音をまき散らさないと走り出さない。
そんな引退寸前のバスがある時から気になって仕方なくなったの
である。
そこである日とうとうお小遣いをためて終点まで行ってみること
にした。いや、一区間だけならすぐにでも乗れたが、それじゃ歩い
ても行ける処までしか乗れないから、降りたところで見慣れた風景
でしかない。それじゃあ、つまらないと考えたのだ。
でも、案の定というか、町を離れた処で車掌さんに声をかけられ
た。
「おい坊主、今日はどこへ行く。あんな田舎におまえ知り合いで
もいるのか?」
こちらから見れば見かけない人だが、何しろ営業所管内では有名
人だからすぐにわかってしまうのだ。
「何にもないよ。このバスに乗りたかっただけだから」
「このボロにか?物好きだなあ、おまえ」
「だって珍しい形してるから」
「珍しい?…そうか、お前、知らないんだ。昔はバスっていった
らみんなこんな形してたんだぜ。お前、バスって始めからマッチ箱
みたいだって思ってたんだろう。そう言やあ、こいつもそろそろ廃
車になるって言ってたなあ。あそこもついに田舎から卒業ってわけ
だ。めでたし、めでたしだな」
「帰りのバスはいつ出るの?」
「向こうに着いて10分後。おまえ、どうせ行って戻って来るだ
けだろう?」
「うん」
「だったら、そのままここに乗ってな。誤車扱いにしてやるから。
無駄に小遣い使うことないだろう」
こんな会話があって、向こうに着いたらほんのちょっと散歩して
同じバスで帰ってきた。それだけの旅だがこれが不思議に楽しい。
でも料金はちゃんと払ったよ。そういう事だけはきっちりしている
質屋の息子だったのである。
その日私は駐車場の隅にぽつんと置かれたボンネットに目を留め
る。普段なら「なんだボロバスかあ」で終わりだが、その日に限っ
ては、まるでそのオンボロバスが私を呼んでるような気がした。
今でこそどこにもいなくなってしまったからみんなで「懐かしい」
なんて言って乗りに行くけど、当時の常識ではボンネットの走る処
はど田舎。
「お前んとこまだボンネットかよ」なんてバカにされたもんだっ
た。
営業所で見かけたこのバス、型式も古そうだし、いつ見てもタイ
ヤやボディーが泥だらけ。エンジンを掛けると人一倍黒い煙を出す
し、走り出す瞬間も、「おや壊れたんじゃないか」って心配するほ
どもの破裂音をまき散らさないと走り出さない。
そんな引退寸前のバスがある時から気になって仕方なくなったの
である。
そこである日とうとうお小遣いをためて終点まで行ってみること
にした。いや、一区間だけならすぐにでも乗れたが、それじゃ歩い
ても行ける処までしか乗れないから、降りたところで見慣れた風景
でしかない。それじゃあ、つまらないと考えたのだ。
でも、案の定というか、町を離れた処で車掌さんに声をかけられ
た。
「おい坊主、今日はどこへ行く。あんな田舎におまえ知り合いで
もいるのか?」
こちらから見れば見かけない人だが、何しろ営業所管内では有名
人だからすぐにわかってしまうのだ。
「何にもないよ。このバスに乗りたかっただけだから」
「このボロにか?物好きだなあ、おまえ」
「だって珍しい形してるから」
「珍しい?…そうか、お前、知らないんだ。昔はバスっていった
らみんなこんな形してたんだぜ。お前、バスって始めからマッチ箱
みたいだって思ってたんだろう。そう言やあ、こいつもそろそろ廃
車になるって言ってたなあ。あそこもついに田舎から卒業ってわけ
だ。めでたし、めでたしだな」
「帰りのバスはいつ出るの?」
「向こうに着いて10分後。おまえ、どうせ行って戻って来るだ
けだろう?」
「うん」
「だったら、そのままここに乗ってな。誤車扱いにしてやるから。
無駄に小遣い使うことないだろう」
こんな会話があって、向こうに着いたらほんのちょっと散歩して
同じバスで帰ってきた。それだけの旅だがこれが不思議に楽しい。
でも料金はちゃんと払ったよ。そういう事だけはきっちりしている
質屋の息子だったのである。
(1/30) 書斎
(1/30) 書斎
私の家は例の学校からはかなり離れた処にあって、子供の足だと
電車バスを乗り継いでもゆうに1時間はかかった。この1時間とい
うのが大事で、当時の学校の内規ではこれ以上遠い処からは通えな
いことになっていたのである。
このため母は最初だけでも学校近くにアパートを借りて近くに移
り住もうかなどと本気で考えていた。
でも、そのもくろみをうち砕いたのが、私の無類のバス好き電車
好きだった。私は「バスや電車に乗れないんなら学校へは行かない」
とさえ言い放ってだだをこねたのである。
ただ、最初の頃は時間がかかってもすべてバスで通した。電車を
利用すると早くは着くのだが、2回も乗り換えが必要でまとまった
自分の時間が取りにくいから困るのである。
実は私、幼稚園当時から『バスや電車の中が一番心安らぐ』とい
う不思議な少年だった。母も、教師も、友だちも…それら人たちが
ことさら嫌いというのではないのだが、そばにいるとうざったい気
がして一人でいられる時間がほしかったのである。
(だから孤立児なんて言われてしまうのだが……)
もちろん何度も述べているように運転手さんや車掌さんとは仲良
しだった。だから何かやってるとすぐにちゃちゃを入れてくる事も
多かったが、乗客が残り数人となる地元営業所近くにならなければ
お互いおしゃべりはしないという不文律はできあがっていたから、
それはそれほど気にはならなかった。
私はこの狭い空間で宿題をし、絵を描き、小説を書き作曲までし
ていた。いわばここが私の書斎代わりだったのである。この書斎で
過ごす40分間が私には貴重だったのである。自宅近くの営業所か
ら出る最も長い路線で終点まで乗って行き、そこで別の路線に乗り
換えて15分。さらに歩いて10分。
今にして思えば一時間半もかけてよく通ったなあと思わないでも
ないが、何事も慣れの問題で通っていた当時はそれほど苦痛を感じ
たことはなかった。それもこれもこの激しく揺れる狭い書斎あって
のことだったのかもしれない。
当時は私の街から遠くの学校へ通おうなんて物好きは我が家だけ
だったから物珍しさもあったのだろう。狭い管内だけの話だが、私
は常にアイドルだった。
ところが、四年生になると私の前にライバルが現れる。私の指定
席にもう一人同じ制服を着た少年が無遠慮にも隣に座るようになる
のだ。こいつは、私と名字が同じということもあって最初から妙に
馴れ馴れしく初めは邪険にしていたのだが、そのたびに「ほら兄弟
なんだから」と車掌さんに言われて仕方なくそばにおいてやること
にした。
しかし、何より不満だったのは彼の方が私より数段可愛いという
事。たちまち車内アイドルの座は何も知らない弟に奪われてしまっ
たのである。
私の家は例の学校からはかなり離れた処にあって、子供の足だと
電車バスを乗り継いでもゆうに1時間はかかった。この1時間とい
うのが大事で、当時の学校の内規ではこれ以上遠い処からは通えな
いことになっていたのである。
このため母は最初だけでも学校近くにアパートを借りて近くに移
り住もうかなどと本気で考えていた。
でも、そのもくろみをうち砕いたのが、私の無類のバス好き電車
好きだった。私は「バスや電車に乗れないんなら学校へは行かない」
とさえ言い放ってだだをこねたのである。
ただ、最初の頃は時間がかかってもすべてバスで通した。電車を
利用すると早くは着くのだが、2回も乗り換えが必要でまとまった
自分の時間が取りにくいから困るのである。
実は私、幼稚園当時から『バスや電車の中が一番心安らぐ』とい
う不思議な少年だった。母も、教師も、友だちも…それら人たちが
ことさら嫌いというのではないのだが、そばにいるとうざったい気
がして一人でいられる時間がほしかったのである。
(だから孤立児なんて言われてしまうのだが……)
もちろん何度も述べているように運転手さんや車掌さんとは仲良
しだった。だから何かやってるとすぐにちゃちゃを入れてくる事も
多かったが、乗客が残り数人となる地元営業所近くにならなければ
お互いおしゃべりはしないという不文律はできあがっていたから、
それはそれほど気にはならなかった。
私はこの狭い空間で宿題をし、絵を描き、小説を書き作曲までし
ていた。いわばここが私の書斎代わりだったのである。この書斎で
過ごす40分間が私には貴重だったのである。自宅近くの営業所か
ら出る最も長い路線で終点まで乗って行き、そこで別の路線に乗り
換えて15分。さらに歩いて10分。
今にして思えば一時間半もかけてよく通ったなあと思わないでも
ないが、何事も慣れの問題で通っていた当時はそれほど苦痛を感じ
たことはなかった。それもこれもこの激しく揺れる狭い書斎あって
のことだったのかもしれない。
当時は私の街から遠くの学校へ通おうなんて物好きは我が家だけ
だったから物珍しさもあったのだろう。狭い管内だけの話だが、私
は常にアイドルだった。
ところが、四年生になると私の前にライバルが現れる。私の指定
席にもう一人同じ制服を着た少年が無遠慮にも隣に座るようになる
のだ。こいつは、私と名字が同じということもあって最初から妙に
馴れ馴れしく初めは邪険にしていたのだが、そのたびに「ほら兄弟
なんだから」と車掌さんに言われて仕方なくそばにおいてやること
にした。
しかし、何より不満だったのは彼の方が私より数段可愛いという
事。たちまち車内アイドルの座は何も知らない弟に奪われてしまっ
たのである。



 ほのぼのとしたSP小説が魅力的なサイトです。
ほのぼのとしたSP小説が魅力的なサイトです。
 私はこの方のイラストが大好きなんです。
私はこの方のイラストが大好きなんです。
 『お尻叩きの物語』(kurakuさん)
上手な文章の小説が魅力です。
空気感の様な物が私と似ている
気も…今は休止中のようです
が、復活期待大のブログです。
『お尻叩きの物語』(kurakuさん)
上手な文章の小説が魅力です。
空気感の様な物が私と似ている
気も…今は休止中のようです
が、復活期待大のブログです。
 純喫茶って感じのブログです。
この方の小説は心が和みます。
特に「連絡帳」は私のお気に入りです。
現在休止中なのが残念です。
純喫茶って感じのブログです。
この方の小説は心が和みます。
特に「連絡帳」は私のお気に入りです。
現在休止中なのが残念です。
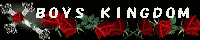
 下手な絵でお恥ずかしいのですが、一応、うちのバナーです。
下手な絵でお恥ずかしいのですが、一応、うちのバナーです。